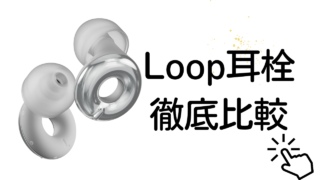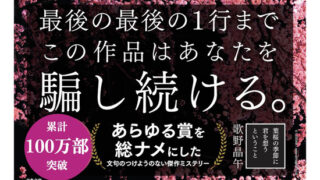こんにちは、みなさん!今日は、私たちの日常生活に大きな影響を与えている「認知のゆがみ」について、詳しくお話ししていきます。
「え?認知って認知症のこと?」なんて思った方、安心してください。今回お話しする認知のゆがみは、若い人にも関係する重要なトピックなんです。😊
認知のゆがみって何?🤔
認知のゆがみとは、簡単に言うと、「現実を歪めて捉えてしまう思考パターン」のこと。私たちの脳が、ある種のショートカットを使って情報を処理する中で生まれてしまうんです。
例えば、「今日は最悪の日だ」と思ってしまったり、「私はいつも失敗ばかりする」と決めつけてしまったり…。こういった考え方、心当たりありませんか?
実は、こういった思考パターンは誰にでもあるんです。でも、それが強くなりすぎると、日常生活に支障をきたすことも。だからこそ、自分の中にある認知のゆがみに気づき、向き合うことが大切なんです。
よくある誤解:認知のゆがみ≠発達障害❗
「認知のゆがみ=発達障害」と思っている人もいるかもしれません。確かに、発達障害の方は認知のゆがみが強く出ることがありますが、これは全ての人に共通する心の傾向なんです。健常者も発達障害者も、程度の差こそあれ、みんな持っているものなんですね。
認知のゆがみの10種類:あなたはどのタイプ?🧐
認知のゆがみには、主に10種類あります。一つずつ見ていきましょう。
- 白黒思考
「完璧か失敗か」といった極端な考え方をしてしまうこと。グレーゾーンを認めない思考パターンです。
例:「試験で100点取れないなら、勉強する意味がない」 - 過度の一般化
一度の出来事から、すべてがそうだと結論づけてしまうこと。
例:「一度失敗したから、私は永遠に成功できない」 - 心のフィルター
ネガティブな面ばかりに注目してしまい、ポジティブな面を無視してしまうこと。
例:「10個の褒め言葉をもらっても、1つの批判だけが気になる」 - マイナス化思考
良いことを無視し、悪いことばかりを強調してしまうこと。
例:「昇進できたけど、きっと運が良かっただけだ」 - 結論の飛躍
根拠なく悪い結論を導き出してしまうこと。
例:「彼が電話に出ないのは、きっと私のことを嫌いになったからだ」 - 拡大解釈と過小評価
悪いことを大げさに、良いことを過小評価してしまうこと。
例:「小さなミスを犯したら「人生終わった」と思う一方で、大きな成功を「たまたま」と片付ける」 - 感情的決めつけ
感情を事実と同一視してしまうこと。
例:「不安だから、きっと何か悪いことが起こるに違いない」 - 〇〇すべき思考
「〜すべき」「〜ねばならない」と自分を縛ってしまうこと。
例:「常に笑顔でいるべきだ」「失敗は絶対にしてはいけない」 - レッテル貼り
一つの特徴で人全体を判断してしまうこと。
例:「一度嘘をついた人は、永遠に信用できない嘘つきだ」 - 個人化
自分に関係のない出来事まで、自分のせいだと思ってしまうこと。
例:「友達が落ち込んでいるのは、きっと私が何か悪いことをしたからだ」
これらの認知のゆがみ、どれか心当たりがありましたか?実は、これらは相互に関連していて、一人の人が複数のパターンを持っていることも多いんです。
認知のゆがみとの向き合い方💡
認知のゆがみに気づいたら、どうすればいいのでしょうか?完全になくすことは難しいかもしれませんが、以下のステップで少しずつ改善できます:
- 自分の思考パターンに気づく
日記をつけたり、友人と話したりして、自分の思考を客観的に見つめ直してみましょう。 - 思考を疑ってみる
「本当にそうだろうか?」と自問自答してみましょう。 - 別の視点を探す
友人や家族に相談して、違う角度からの意見をもらってみましょう。 - 肯定的な面にも目を向ける
良いことも悪いことも、バランス良く見るよう心がけましょう。 - 自己compassionを育てる
自分に優しくすることを学びましょう。完璧を求めすぎないことが大切です。
実際の体験談:Aさんの場合📝
私の友人のAさん(30歳・女性)は、典型的な「白黒思考」の持ち主でした。
ある日、Aさんが仕事でちょっとしたミスをしてしまいました。上司からは「気をつけてね」と軽く注意されただけだったのですが、Aさんは「もう私はダメな人間だ。仕事を辞めるべきだ」と深刻に悩んでしまったんです。
これは明らかに現実とかけ離れた反応でしたよね。でも、Aさん本人は本当に苦しんでいたんです。
そこで、私はAさんにこう提案しました。「ちょっと考え方を変えてみない?完璧か失敗か、の二択じゃなくて、その間にあるグレーゾーンも認めてみたら?」
最初は戸惑っていたAさんでしたが、少しずつ自分の思考パターンに気づき始めました。「ミスは誰にでもある。これを機会に成長できるかもしれない」と考えられるようになったんです。
今では、Aさんは以前ほど極端な反応をしなくなりました。完璧を求めすぎず、失敗も成長の機会として捉えられるようになったんです。これぞ、認知のゆがみとの上手な付き合い方ですね!
みなさんへのメッセージ💌
認知のゆがみは、誰にでもあるものです。それを持っていること自体は決して悪いことではありません。大切なのは、自分の中にある認知のゆがみに気づき、それとどう付き合っていくかを学ぶことなんです。
一朝一夕には変わりませんが、少しずつ自分の思考パターンを見つめ直し、より健康的な考え方を身につけていくことで、きっと人生はもっと豊かになるはずです。
そして、周りの人たちへ。身近に認知のゆがみで苦しんでいる人がいたら、その気持ちに寄り添ってあげてください。理解と共感が、大きな支えになります。
最後に…✨
どんな思考パターンを持っていても、あなたはあなたのままで素晴らしいんです。ただ、もし今の考え方で苦しんでいるなら、少しずつでいいので変化を試みてみてください。
小さな気づきや行動が、あなたの人生を大きく変える可能性があります。一緩に、でも着実に、自分のペースで前に進んでいってくださいね。
応援しています!
みなさんは、自分の中にどんな認知のゆがみがあると思いますか?もし良ければ、コメント欄で共有してくださいね。みんなで理解を深め、より健康的な思考パターンを身につけていけたら素敵ですね!
本の紹介
概要
本書は、私たちの心の不調やストレスの多くが「認知のゆがみ」によって引き起こされていることをわかりやすく図解で解説しています。
認知行動療法(CBT)の考え方に基づき、「白黒思考」「自己関連付け」「過度の一般化」など、代表的な10のゆがみに焦点をあて、それぞれの特徴・直し方を丁寧に紹介。心理学の専門知識がない人でも理解しやすく、日常での実践に役立つ内容です。
感想(簡単に)
図が多くてとにかく読みやすい!
「自分にもこういう思考のクセあるかも…」と気づける内容が多く、セルフチェックにも◎。メンタルがちょっと疲れているときや、考え方を整えたいときに手元にあると安心できる一冊です。
特に「思考の偏りに気づくだけでもラクになる」というメッセージが印象的でした。